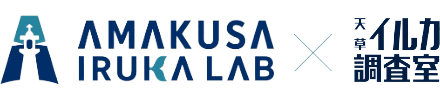SDGs 天草のイルカはこれからどうなる?今はどんな時代で何を目指していけばいいのか、イルカの聖地で考えるこれからの共生社会

イルカの住む天草の海
有明海には現在、2種類の鯨類、ミナミハンドウイルカとスナメリが定住しています。そして、天草下島、主に通詞島から鬼池、南島原に囲まれたエリアは内海と外海をつなぐ水路になっていて、早崎瀬戸海峡と呼ばれています。ここは海流が速いことで知られ、まさにイルカたちが生息している場所です。海の食物連鎖の頂点である鯨類が内海(限られたエリア)に定住(生涯を過ごす)できるのは、それを支えるすべての階層の いのち に支えられているからです。
イルカがいる=豊かさの象徴 というのは、イルカが住めるほど海が豊かだ、ということです。普段は気にも留めない、「すべての要素」がそれを支えています。
自然界に起こるすべては、お互いに共存していくための出来事です。自らの種が縮小、あるいは絶滅するような争いや奪い合いをする必要はなく、それぞれのいのちを全うしています。
【イルカがいる】という事象から、その背景まで思いをはせることができる人たちはいったいどのくらいいるのでしょうか。それは、私たち自身が生きている、生きていられる、ことの背景を想像できるかどうかと同じことかもしれません。
美しく潔く、気高い
イルカたちと過ごしていると、私にはそんな気持ちが体中から湧いてきて、ただただ圧倒されます。みなさんはいかかですか?イルカが好きかどうかに関わらず、イルカたちの姿に影響を受ける人は少なくありません。
元気になれるとか、癒されるとか、会ってみたい、一緒に遊びたい、そういった表現も根源は同じで、それぞれに自分のいのちが 何か に反応しているんだと思います。
その 何か は量子力学などの物理の世界で少しずつ解明されはじめている部分もありますが、まだまだ不思議がいっぱいです。しかもイルカやくじらは、いろいろな側面から世界的にもカリスマの動物なのです。
宝物が抱えるジレンマ
多くの人が、すでに頭ではわかっていること。それは、彼らの生息環境がとても厳しいだろうということです。そして実際に数も減少しています。現状を考えれば、当然の成り行きです。
さて、天草の人たちにとっては、なんでもない「野良イルカ」が、いつの間にか「宝物」と呼ばれるようになっている。そして(その定義や個人の価値観はさておき)それを宝物扱いするにしても、なんだか危機らしい、ということなんです。
当たり前にそこにいるからこそ、気が付くこともなかった、気になることもなかったイルカたち。なぜ宝と呼ばれるのか?それは、【観光事業における】経済効果のみを意味しているわけではないことは、もうおわかりだと思います。イルカたちは海の豊かさのバロメーターだからです。
もともとは、「減少しつつあってやばいから大切にしなくちゃいけない宝」(希少)ではないのです。イルカたちがいる豊かな海、という価値が故に、宝(シンボル)であるはずだったのです。
イルカたちはいます。まだここに生きています
危機的状況にあり、数は減りながらも、イルカたちはまだ早崎瀬戸海峡に住み続けています。なくなったら、取り戻すことはできない宝物は、まだ、私たちのそばにあります。手のひらから少しずつこぼれ落ちていく砂のような状態ではあっても。今まだ、ここにいます。
2019年12月、いまの思いを書き残しておこうと思います。
イルカの海があり続けてほしい
天草は今
野生のイルカが生息する環境が現存している=奇跡
と
ただし辛うじて=課題
という状況です。
それをふまえて、これからも【天草に野生のイルカが住み続けてほしい】のです
かつては当たり前に、海のエネルギーが高かった時代が続きました。そこに人為的な負荷がかかっても、自然の流れのなかで緩衝還元されてきました。しかし、現代は自然のその力(弱まったとは思わない)よりも、人の影響、負荷のほうががあまりにも大きくなりすぎました。SDGs #14にもありますが、レジリエンスを回復する取り組みが必要です。そのなかで私は、自然の力を回復するというよりは、ただシンプルに、人の営みのなかで“やめること”を見出す、ことではないかと考えています。
本来の自然の力は人が考え付くあらゆる奇跡よりも、強大で神秘的で超越しているわけなので、それが引き出される循環に蓋をしていることを取り去ればいいだけ。そう思うのです。
私たちにとって、実は必要のないことをやめるだけでいいと思います。具体的にどうしていくのがいいのでしょうか。解決策をもっともっと明確にして、大きなパワーで進めることができたらと願わずにはいられないのです。
残念ながら、まだ天草にはイルカに関する公式な拠点がありません。(詳しい人がいない、データがない、研究所がない)そのため、
イルカを知る、伝える、考える機会がない
イルカが自然の営みの一部であるという視点がない
オーバーツーリズムによる弊害(無法地帯、事業活動=自然破壊の図式)
ハラスメントによる弊害(ハラスメントの実害+ハラスメント意識の欠落)
自然環境そのものの危機など課題が山積しています。今はまだ、これまでの状況のお釣りのような恩恵を辛うじて受けているので、それがあるうちは危機に気が付きにくい。
そんな天草の現状において、イルカが住んでいるという奇跡的な状況が続くためにできることは何か、それを問い続けています。正解はないけれど、やれることをひとずつチャレンジしてみるしかない。
これまでの力と先人たちの営みに感謝しながら、 現実に向き合い、アップデートしていく時期だと思うし、そうしていきたい、きっとできると考えています。
現実に向き合い、アップデートしていく時期だと思うし、そうしていきたい、きっとできると考えています。 彼らと遊び、彼らと学び、彼らと生きていきたい、これからも!
彼らと遊び、彼らと学び、彼らと生きていきたい、これからも!

令和元年、今年もあっという間に過ぎました。何をやれたかな。種まきをしている活動の伏線はきっとそのうち意味がみえてくるはず!わくわくしながら、来年も進んでいきます。
イルカラボに関わってくださるすべての皆様に心からお礼申し上げます。

ありがとうございました。
よいお年をお迎えください!
**************************

天草イルカラボでは、SDGsの普及、推進活動をしています。
くまもとアイランドキャンパス事業の売上げの一部はイルカラボ活動の支援に使われます。
https://www.island-campus.com/
-
前の記事

天草みつばちラジオ 2019年最後の出演もイルカで大騒ぎ 2019.12.22
-
次の記事

新年のご挨拶 2020.01.01